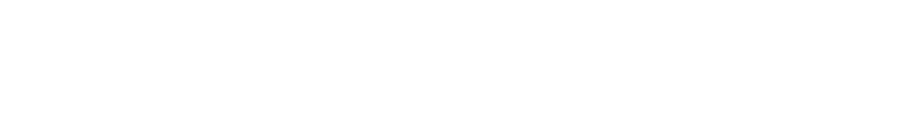アートフェアアジア福岡2025(AFAF2025)(9月26日〜28日)、に行ってきたので感想でも書こうと思います。前回はおそらく2019年くらいに行きました。
アートフェアアジア福岡とは2015年から続く、日本で唯一アジアをコンセプトにしたアートフェアです。
コンセプトはアジアと日本をつなぐアート交流の場、アジアの多様性を感じさせるフェアとしてギャラリーやアーティストを集めています。
公募・アワードなども組み込む試みもあるようで、「AFAF AWARD powered by E.SUN BANK」という公募展も復活しているとの記述があります。福岡市との連携、街を巻き込むアートプログラム(FaN Week など)とも切り結びながら運営されているようです。
今年で記念すべき10回目の開催で、マリンメッセ福岡B館(展示ホール)のダイナミックなブース展示でした。
福岡でこうした国際的な規模のアートイベントがあること自体とても嬉しいことだと思いますし、実際に会場に行って色々な感情が湧きました。
せっかくなので良かったことと気になったこと、両方書こうと思います。
好きな作品を見つけたり、アーティストから直接話を聞けたことはよかったと思います。
また、福岡という地方都市でここまで多様な作品に触れられること自体、大きな意味があると思いました。

一方でどうしても拭えない違和感もありました。
VIP受付があったり、高額な作品が並び業界人やコレクターの存在感が強く、一般来場者は“買わない観客”としての立場に追いやられてしまうような感じ。
「アジア交流」と掲げながらも、実際には“売れる作品を揃えた商談の場”に見えてしまう瞬間がありました。アートが本来持つはずの自由さや普遍性よりも、業界の利害や政治的な空気が先に立ってしまっている気がします。
「アジアの交流」というキャッチコピーを掲げたことで、来場者は「国際的な文化交流」や「アジアの多様性を感じられる展示」を期待しました。けれど実際にはギャラリーとコレクターのための場=業界向けの商談会の色が濃く、一般客からすると「アジアの交流要素どこ?」という感じだと思います。
これはマーケティング的に見ると期待と実態のギャップを作ってしまったという問題じゃないかなと。
ただ業界向けに割り切っていたら良かったかといえばそれもまた違うと思うんです。
なぜなら、それはそれで「アートが一般社会に根づかない」最大の原因になってしまうからです。
アートは誰にでも開かれているべきであると個人的に思っています。にもかかわらず、今のフェアの在り方はむしろ“遠ざける仕組み”に見えてしまいました。