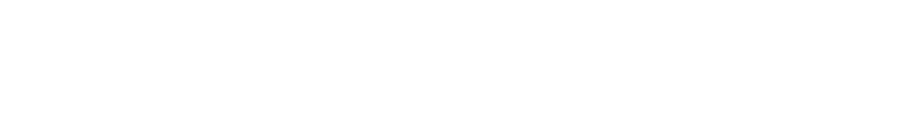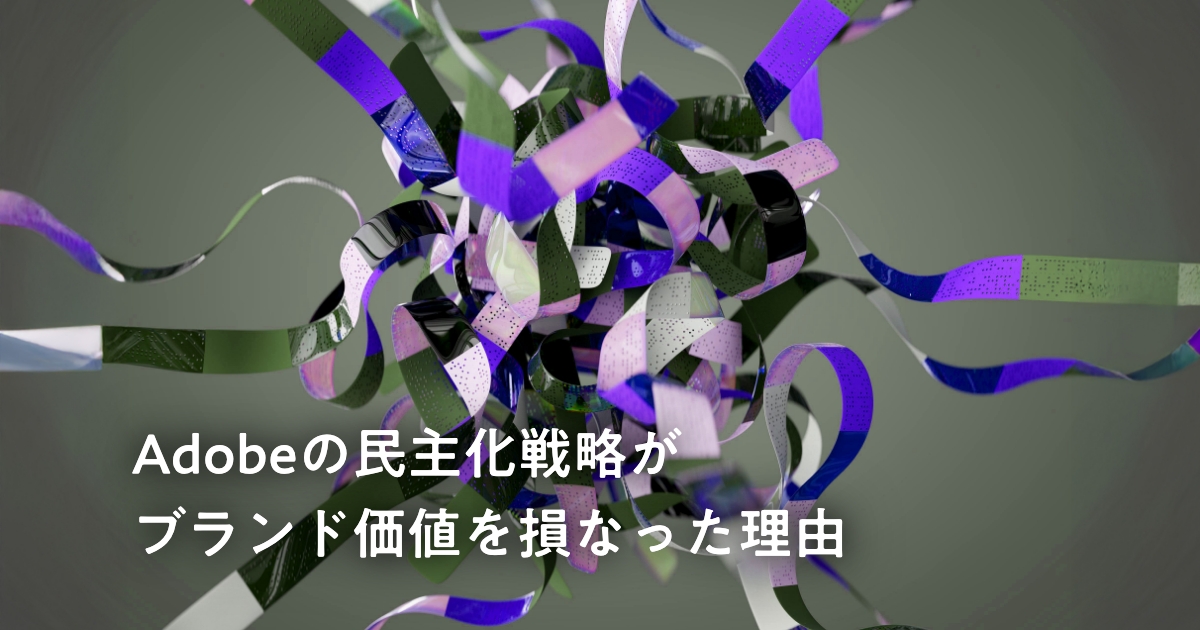めずらしくデザインとブランディングについての話です。
最近、「『Affinity』がまさかの無料化──フォトショップ対抗アプリの最右翼」というニュースが目に留まりました。
ざっくり言うと、CanvaがSerifを買収してAffinityを無料化したという内容です。
CanvaやFigmaを使いながらもAdobeにも長年関わってきたクリエイターなら、このニュースをかなりリアルに感じたのではないでしょうか。
このニュースからAdobeの民主化戦略がブランド価値を損なった理由について紐解いていこうと思います。
CanvaによるSerif買収とAffinity無料化の背景
Canvaは2024年3月にSerifを買収し、Affinityブランドを手中に収めています。(記事)
この買収によりCanvaは「初心者/ノンデザイナー向け」のビジュアルツールという立ち位置から、プロ/クリエイター向け本格的なデザインツールの方向へも本格参入しようとしていると分析されています。(記事)
Affinity側もより速く、強力な機能を届けるためにCanvaのリソースを活用するという意図を明かしています。(記事)
結果的に、Canvaは“ライト層 × プロ層”両方をカバーできる唯一の存在へと変化しつつあります。
Adobe一強だった構図に、初めて(多分?)現実的な対抗軸が生まれたのではないでしょうか。
Adobeの現在地:Figma買収失敗の意味
少し遡るとAdobeは2022年にFigmaを約200億ドルで買収する合意を発表しました。(記事)
しかし2023年末、規制当局の承認を得られず現実的な道が見えないと判断して撤退しています。(記事)
しかも買収失敗により、AdobeはFigmaに10億ドルの解消料(いわゆるペナルティや違約金的なもの)を支払うことになっています。 (記事)
なぜ買収失敗したのか
主な阻害要因は以下の通りです。
規制当局(特に欧州連合の European Commission と英国の Competition and Markets Authority(CMA))が「AdobeがFigmaを買収することで、デザインツール市場(特にUI/UX設計・プロトタイピング領域)において競争が大きく損なわれる可能性がある」と懸念しました。 (記事)
規制当局が注目したのは将来の競争(future competition)という概念で、たとえ現在競合関係が薄くても、Figmaが成長することでAdobeの競争相手になりうるという観点が重視されました。 (記事)
また、買収発表直後から「買収金額が過大評価ではないか」「AdobeがFigmaを自社製品に吸収して改悪するのではないか」という懸念もデザインコミュニティ側から出ていました。(記事)
そしてあれだけの金額を提示していたがゆえにAdobeが市場支配力をさらに強めるという論点が規制当局にとって重大な解約要因となりました。
この買収が市場構造を大きく変える可能性があり、規制的に許可が出ないという構造的な壁が買収にストップをかけた主因です。
結果として、金額・評価額・負担・リスクの全てが「買収後の統合が可能かどうか」「規制をクリアできるかどうか」という観点で再検討され、両社とも道筋がないと判断しました。
↑これ巨大テック企業の買収では最近とても多い現象なんです。特に欧州(EU)やイギリスのCMAは近年かなり厳しくなっていて、「将来的に競争を減らす可能性がある」だけでもブロック(承認しない)する傾向があります。
なぜAdobeが道筋がないと判断したのか
企業買収というのは単に「両社が合意したからOK」ではなくて、その後に各国の独占禁止法(antitrust law)に基づく審査が必要になります。
特に国際企業の場合、アメリカ、欧州連合(EU)、イギリス、カナダ、日本など複数の国・地域すべての承認を得なければならないんです。
AdobeとFigmaのケースでは、EUとイギリスが「この買収はクリエイティブツール市場の競争を著しく損なう恐れがある」として調査を強化。その審査が長期化・複雑化し、Adobe側が「これ以上進める現実的な道が見えない」と判断したという経緯です。
つまりAdobeとFigmaが自ら合意を解消したという形です。明確な道筋がないってことです。
表向きは両社で協議の結果という柔らかい言い方ですが、実際にはこれ以上進めても承認は下りないと悟った、というのが本音に近いでしょう。
背景にはGAFA規制の流れもあると思います。GoogleやMetaなどの独占問題が世界的に問題視されて以降、各国が大企業による市場支配をより厳しく見ています。その流れでAdobeの買収もまた同じ構図では?と警戒されたんですね。つまり「承認を得られそうにない=先が見えない」から撤退というのがAdobeのFigma買収撤退の真意です。
実はこの「自主撤退」という形は、企業ブランドを守るためのやや上品なやり方でもあります。
規制で止められたと報道されるより、双方の合意で終了としたほうがダメージが少ないですし。
この件はブランディングの観点から見ても興味深いです。技術的失敗とかではなく政治的・信頼的な理由での撤退ですから、「企業ブランドの信頼が国境を超えて影響する」現代的なケースとも言えます。
Adobeの「民主化」とブランド崩壊
Adobeは近年、「クリエイティブの民主化(誰でもデザインできるように)」を掲げてきました。
モバイルアプリ、クラウド連携、AI生成などを一般層に広げた結果、プロ向けの敷居を下げすぎたのです。
結果として、
・プロのツールというステータス性が薄れた
・高額なサブスクへの不満が増えた
・“憧れ”が“依存と不信”に変わった
という典型的なブランド・コントラディクション(矛盾による崩壊)を引き起こしました。
「民主化」を掲げた企業が、自らの民主化によって王座を脅かされている。まさに皮肉です。
ユーザーの「囲い込み」から「不信」へ
AdobeはCreative Cloud化によって安定収益を得ましたが、同時に「解約しづらい、違約金が高い」などユーザー体験の悪化を招きました。
私は以前Adobe Stockを解約しようとして9,000円払ったことがあります。あれは正直ブランド体験としてマジで最悪でした。
この囲い込みの積み重ねが「もうAdobeに縛られたくない」という感情を生み、CanvaやAffinityへの移行を後押ししています。
支配はブランドではありません!!!
ブランドとは信頼であり、支配から解放された瞬間に反動が起きる。今それが起きています。
デザイン業界の構造変化
印刷の現場では依然としてAdobeが共通言語ですが、WebやSNSでは「Illustratorを使わなくても成立する」状況が加速しています。
つまり「Adobe=必須」の時代が終わりつつあるということです。
ブランディング視点から見たAdobeの誤算
Adobeはかつてプロ専用ツールという排他性を武器にしていました。
しかし「誰でも使える」戦略によって、短期的なユーザー数拡大は成功しても、長期的には“憧れのブランド”を手放したのです。
ブランドとは「全員に使われること」ではなく、「選ばれる理由を守り抜くこと」です。
Adobeはそこを見誤った結果、今の状況を招いています。
“デザインの価値”を下げた責任
デザインは本来、思考と構築の技術であって、操作スキルの仕事ではありません。
けれどもコロナ禍をきっかけに「どこでもできる」「すぐになれる」といった広告が溢れ、デザインの本質が“手軽なスキル”にすり替えられていったと感じます。
Adobeはその流れを加速させ、「創造性を支える会社」から「生産性を搾り取るサブスク企業」へと変わってしまいました。結果的に“デザインの価値”を自ら押し下げる形となったのだと思います。
まとめ:民主化の先に見えたブランドの限界
このまま行くとAdobeは「プロ専用ツールの象徴」ではなく、「AIを軸にした総合クリエイティブ企業」として再定義されていくと思います。それは時代の流れとして自然な変化かもしれません。
ただ、ブランディングの視点で見れば、“誰でも使える”戦略はブランド価値を広げると同時に、選ばれる理由を薄めるリスクも伴います。Adobeはその境界をとっくに越えてます。
Canva+Affinityは「下から上へ」伸びる構図で成長し、Adobeが築いてきた特別な領域を侵食し始めています。それは市場の自然な流れであり、同時にブランドのあり方を問い直す転換点でもあります。
そしてこの「ツールの民主化」がもたらす、スキルやクラフトマンシップの価値の変化については、別の記事で改めて書こうと思います。
![Affinityの教科書[V2対応]](https://manson-art.com/wp-content/themes/stile/assets/img/trans.gif)
Affinityの教科書[V2対応]
単行本 – 2023/6/21
堀江ヒデアキ (著)

Canva使い方入門 (ENJOY DESIGN)
単行本 – 2023/12/6 mikimiki web school (著)